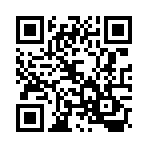2009年12月12日
タイムス中国茶教室 【第2回:2009/11/14】

2回目のお教室のテーマは、中国茶の歴史、名称、淹れ方。
しかし前回同様、中国四千年の歴史はあまりにも膨大すぎて、はしょることさえ無理。
そんなわけで今回も試飲したお茶の画像のみをご紹介します。
 | のある画像はクリックすると拡大します。 |
 | 安徽省の黄山毛峰(こうざんもうほう)というお茶で、緑茶に分類されます。 中国十大銘茶のひとつ。 白い産毛が多いほど高級とされ、中国本土でも一般的なお茶屋さんでは入手できないそうです。
先生がお持ちくださったのは最高クラスの特級品。 |

▲黄山毛峰。
水色はこの茶葉の色から想像できるように、ごく薄いレモンイエロー。
お味は渋みはなく、まろやかで、甘みを感じました。
主張しすぎず、人によっては少々物足りなく感じるかも。
 | お茶を淹れた後の黄山毛峰。 製茶される前の青々とした葉を想像できるかのよう。 この採取した時のままの茶葉の形を雀舌と形容するそうです。 スズメの舌なんてうまいこと言いますね。 |
 | 雲南省の感通茶(かんつうちゃ)というお茶で、緑茶に分類されます。 大理感通寺というお寺の茶畑で採れたお茶で、現地で直接購入されたようです。 ネットでもなかなか情報が無く、国内で取り扱っているお店はありません。
現地でしか入手できない貴重なお茶です。 |

▲感通茶。
水色はレモンイエロー。
それほど透明感があるわけではないのは、糖度があるせいでしょうか。
黄山毛峰よりは甘みを感じました。とろりとした感じ。
適度な渋みもあって、こっちのほうが好み。
 | 台湾の杉林渓(さんりんしぃ)という烏龍茶で、青茶に分類されます。 丸まった茶葉は、最初の1煎目は飲まずに捨てます。 もともとは洗茶といって製茶や輸送の過程でついたほこりや汚れを落とす目的でしたが、衛生管理の進んだ現代では眠っていた茶葉を起こす、つまり抽出しやすいように茶葉を開かせてやるのが目的です。 |
 | 杉林渓。 渋みがなく、まろやかで甘みがあります。 行きつけのお茶専門店カメリア・シネンシスでも人気のお茶で、日本でもかなりファン多し。
私も大好きなお茶のひとつです。 |
 | 福建省の鉄観音(てっかんのん)という烏龍茶で、青茶に分類されます。 烏龍茶といえば鉄観音というほど、代表的な銘茶です。 日本では某メーカーがペットボトル飲料として発売し、一般的に広まった烏龍茶。 色が濃くてちょっと苦味がある印象がありますが、本当の烏龍茶は蘭のような香りで甘みがあり、清々しいお茶です。
中国十大銘茶のひとつ。 |
 | 鉄観音。 美味しい!これは文句なくとても美味! 先生のお持ちくださるお茶がどれもかなりのグレードを誇る茶葉であるということもあるとは思いますが、いかに某メーカーの刷り込みが強力だったことか。
日本でもこれだけ有名なお茶です。やはり一度は上質の鉄観音を試してみたいものです。 |
 | 江蘇省の碧螺春(へきらしゅん/ぴろちゅん)というお茶で、緑茶に分類されます。 ものすごいたくさんの白い産毛! 一芯一葉の新芽だけを摘むので、生産量が少なくとても貴重なお茶です。 お味は少しスモーキーな感じも。
新芽が多いので水色は少々濁っています。 |
 | アールグレイ。 これは紅茶で、お茶菓子のケーキをいただくために淹れたもの。 アールグレイとは紅茶の茶葉にベルガモットという柑橘類の香りをつけたもの。
もともとは中国のキーマン紅茶(祁門茶)をベースに香り付けをしますが、このアールグレイはインドのダージリンをベースにしたもの。 |
 | お茶菓子は生クリームたっぷりのロールケーキ。 このお菓子に合わせて、お茶は緑茶ではなく先生が紅茶をチョイス。
私としては本当はお砂糖とミルクをいれたいところです♪ |
今回は中国のお茶に関する歴史を背景に、代表的な中国茶を試飲してみました。
杉林渓(さんりんしぃ)は台湾のお茶ですが、烏龍茶の鉄観音との比較ということで。
さすがに名だたるお茶の名産地だけあって、どれも味わい深く美味しいお茶ばかり。
お教室でこれだけ上質のお茶をいただくと、もうそんじょそこらのお茶では満足できません。
味覚って本当に肥えちゃいますね

 タイムスカルチャースクール
タイムスカルチャースクールhttp://www.times-cs.jp/
 2009年10月開講コースでは、中国茶・台湾茶の他に紅茶や日本茶もカリキュラムに含まれています。
2009年10月開講コースでは、中国茶・台湾茶の他に紅茶や日本茶もカリキュラムに含まれています。Posted by りえぴゃん at 05:06
│赤嶺先生お茶講座