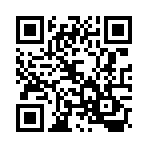2009年12月01日
タイムス中国茶教室 【第1回:2009/10/10】

今年はタイムスの紅茶教室が一度も開催されないようなので、仲の良いお茶好きメンバーと共に中国茶教室を受講することにしました。
最近はすっかりお気に入りのお茶専門店カメリア・シネンシスに入り浸っている私ですが、そこの店主ご夫妻にとっても師匠である赤嶺文弥乃(あかみねあやの)先生が講師です。
県内の中国茶界を牽引する赤嶺先生。
中国茶道陸羽の会を主宰されていて、ご自宅でもお教室を開いていらっしゃいます。
20年近く前になるでしょうか。
那覇市内の某所に点心と台湾茶をいただけるお店があって、当時はひどく珍しいものでした。
今でこそ日航アリビラなどで飲茶を楽しめますが、当時は台湾茶ですら滅多に飲める機会はなかったものです。
その某所のお店で初めて私は台湾工夫式でお茶をいただいたわけですが、そのお店こそが当時赤嶺先生がオーナーだったお店。
オーナー自ら淹れてくれる台湾茶が美味しくて、今でも記憶に残っています。
そんな私の過去と、先生がお店をやってらっしゃったという過去が最近リンクし、
あれっ? ということは、もともと私の台湾茶との出会いは赤嶺先生のおかげだったのね
と、何かご縁のようなものを感じました。

▲20年前から赤嶺先生は私のお師匠さんとして運命づけられていたのでしょうか・・・。
さて今回の中国茶教室。
台湾茶も包括していますが、紅茶や日本茶もカリキュラムに含まれています。
講座名も、優雅で清香のお茶の世界とし、お茶全般を学びます。
これはかなり広範囲に渡る内容で、とても全6回では終了できるものではありません。
が、先生のお持ちくださるお茶はどれも台湾や中国でも一般入手の難しい品質の良いものばかり。
お茶の歴史、淹れ方、茶器、効能などを学べ、その上クオリティの良いお茶を飲めるとなれば、これはとてもお得な講座です。

▲赤嶺先生の講座はとても久しぶりだったようで、このとおりの大盛況。
総勢18名の生徒さんなので、先生おひとりでお茶を淹れるのは無理。
お弟子さん2人がサポートしてくれます。

▲第1回目は、中国茶を製法によって緑茶・白茶・青茶・紅茶・黒茶・黄茶と6種類に分け、それぞれの製法の違いや産地を学び、試飲します。
これだけでも1回の講座ではとても無理。
お茶と一口に言っても製法や産地によってこれだけ味や香りに違いがあるのだ・・・ということを理解していただければ十分だと思います。
以下、先生のお話をダイジェストに書き記すにしてもあまりに膨大なため、試飲したお茶の画像だけをご紹介します。(なにせ中国四千年の歴史ゆえ・・・)

▲中国安徽省産 六安瓜片(ろくあんかへん) 緑茶(不発酵)に分類される

▲台湾産 阿里山(ありさん)の烏龍茶 青茶(半発酵)に分類される

▲左:中国福建省産 白毫銀針(はくごうぎんしん) 白茶(弱発酵)に分類される
右:インド ダージリン産 サングマ茶園 紅茶(完全発酵)に分類される

▲インド ダージリン産 マーガレットホープ茶園 紅茶(完全発酵)に分類される

▲インド ダージリン産 キャッスルトン茶園 紅茶(完全発酵)に分類される
 キャッスルトン茶園の紅茶とともにいただいたお茶菓子は、黒糖入りのホイップクリームたっぷりの自家製ふわふわシフォンケーキ。
キャッスルトン茶園の紅茶とともにいただいたお茶菓子は、黒糖入りのホイップクリームたっぷりの自家製ふわふわシフォンケーキ。それと阿里山のお茶で作ったゼリー。
お茶のゼリーも美味しいものですね。
私はどちらかというと紅茶派なのですが、香り高くマイルドで渋みの少ないお茶もまた味わい深いです。
淹れ方も嗜好もお紅茶教室とはまったく別物であるけれど、いろいろなスタイルを許容し、柔軟な姿勢で楽しむこともまた大切なことだと思います。
正解はひとつじゃない・・・!
コレですよね。
 タイムスカルチャースクール
タイムスカルチャースクールhttp://www.times-cs.jp/
 2009年10月開講コースでは、中国茶・台湾茶の他に紅茶や日本茶もカリキュラムに含まれています。
2009年10月開講コースでは、中国茶・台湾茶の他に紅茶や日本茶もカリキュラムに含まれています。Posted by りえぴゃん at 01:26
│赤嶺先生お茶講座